
ピースワンコの評判を調べている読者に向けて、ピースワンコとは何か、保護犬と里親の仕組み、内部告発の有無や報道の内容、代表の情報、プロジェクトリーダー安倍誠に関する発信、さらに寄付をやめる際の手続きまで、公開情報をもとに客観的に整理します。SNSやメディアで語られる闇という表現や杉本彩の指摘の有無も一次情報をあたって確認し、事実関係を丁寧に検討します。
- 団体の基本情報と活動領域の理解
- 報道や内部告発の論点と公式見解の把握
- 譲渡や寄付に関する実務的な流れの理解
- 判断材料となる一次情報への参照リンク確認
【ピースワンコ】評判の全体像と前提
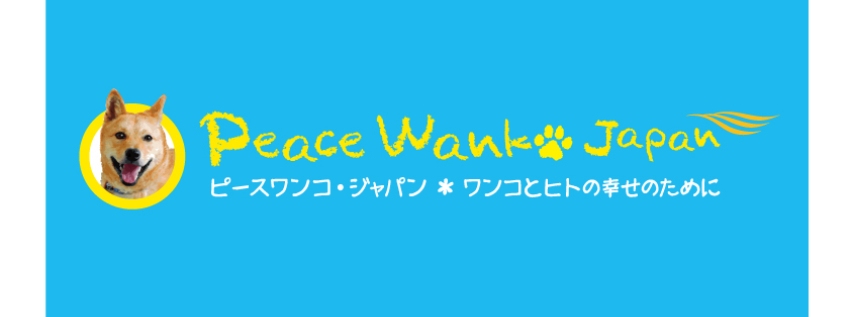
- ピースワンコとは何を指すか
- 保護犬支援の具体的な取り組み
- 里親制度と譲渡の流れ
- 代表の経歴と運営体制
- 安倍誠の役割と発信内容
ピースワンコとは何を指すか
国内の保護犬分野で名前が挙がることの多いピースワンコ・ジャパンは、認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパンが運営するプロジェクト名称です。団体の公式情報では、活動の柱として、自治体からの引き取りを含む保護、健康管理とトレーニング、里親への譲渡、啓発、そして災害救助犬やセラピー犬の育成が掲げられています。こうした複合的な事業構成は、単に一時保護に留まらず、行動評価や社会化トレーニング、再就労に近い「役割付与」まで含めて犬の生涯に寄り添う枠組みをめざす点に特徴があります。加えて、広島県神石高原町のシェルター群や全国の譲渡センター網を活用し、保護から譲渡までの動線を地理的にも機能的にも接続させる運営設計が説明されています。(参照:ピースワンコ公式「活動内容」)
評判の文脈で語られる組織像を正しく把握するには、プロジェクト単体と運営母体の関係を切り分けることが役立ちます。ピースワンコはピースウィンズ・ジャパンの一事業であり、財務や年次報告は原則として運営母体の開示資料に統合されます。これにより、寄付収入・人件費・広報費などの勘定科目は団体全体の枠内で把握されることがあります。評価する立場では、プロジェクト別の開示が行われているか、行われていない場合は該当箇所をどう読み解くかが論点になります。団体側は、不備が指摘された2018年前後の運営課題について、獣医師の増員、データ管理強化、犬舎の増設などの改善策を公表しており、以後の方針も定期的に発信しています。(参照:悪評に対する公式見解/法令順守)
用語メモ:譲渡=保護個体を新たな飼い主へ法的・実務的手続きに則って引き継ぐこと。社会化=犬が人や環境、音、他犬などに慣れ、ストレス下でも安定して行動できるように学習する過程。行動評価=吠え・噛み・分離不安などの課題を専門的に測定すること。保護施設の機能評価では、感染症対策、個体識別(マイクロチップ)、記録管理、収容密度、換気・温湿度管理、トレーニング計画の有無などが重視されます。
インターネット上での評判は、成功事例とトラブル事例の双方が拡散されやすい性質があります。評価を行う際には、①活動スケール(引き取り数・譲渡数・収容能力)、②施設基準(空調、床材、屋外運動スペースなど)、③医療体制(ワクチン、寄生虫予防、手術の可否)、④情報公開(年次報告・会計報告・現場発信)を分けて整理し、時間軸での改善や方針変更の有無を追うと、過去の指摘と現在の実態を区別しやすくなります。公式の説明や定期レポートは、こうした観点を検証する一次情報の入口として有用です。
保護犬支援の具体的な取り組み

公表情報では、保護から譲渡までの各段階で具体的なプロセスが示されています。保護直後は健康チェック、外部・内部寄生虫対策、混合ワクチン接種、マイクロチップ装着、行動評価などの初期対応が行われ、必要に応じて隔離・観察期間が設けられると説明されています。シェルター設備は、各部屋に付随する屋外スペース、共有の中庭、大規模なドッグラン(約80,000㎡の記載あり)、空調(エアコン)や床暖房の完備といったハード面の特徴が紹介され、運動・採光・温湿度管理の観点から環境エンリッチメント(刺激のある環境づくり)を意識した設計がうかがえます。これらの設備は、慢性的ストレスの軽減や、行動問題の予防・改善に資する要素として国際的にも重視されます。(参照:活動内容)
避妊去勢については、幼犬・高齢犬・基礎疾患のある個体など適応が慎重に判断されるケースを除き、順次実施する方針が明示されています。これは、繁殖の防止だけでなく、発情期ストレスや一部疾患リスク低減など、個体の健康と群管理の両面を考慮した運用と位置づけられています。医療行為は獣医師の判断に基づくとされ、既往歴・投薬歴・ワクチン歴などを個体カルテで管理する仕組みが説明されています。(参照:犬の避妊去勢手術について)
確認しておきたいポイント:健康・安全に関わる事項は、自治体の収容施設や譲渡団体で共通して重点管理されます。とくに感染症対策(消毒動線、隔離室の有無、換気計画)と記録管理(カルテ・個体識別・接種歴)は、施設の規模が大きいほど標準化の重要度が高まります。ピースワンコ側は、過去の指摘を受けて獣医師体制とデータ管理の強化を掲げており、犬舎増設やスタッフ増員も含めて飼育密度と動線設計の改善を進めたと説明しています。(参照:法令順守の見解)
シェルター運営では、行動の個別最適化も重要です。人馴れの程度、反応のトリガー(音、視覚刺激、他犬との距離など)、食行動、休息パターンを観察し、ケージレイアウトや散歩ルート、トレーニング頻度を調整するのが一般的です。群管理では、未去勢・未避妊の個体を混合しない、同居犬の相性・年齢差・体格差を考慮する、給餌タイミングと資源ガード(食器や寝床を守る行動)への配慮といった配慮が基本となります。公式情報が伝える運用(未手術個体の雌雄分離など)は、こうした国際的なベーシックにも合致するアプローチと読み取れます。
里親制度と譲渡の流れ
譲渡までのプロセスは、多段階での適合確認を前提としています。一般的な流れとしては、サイト等での情報閲覧・面会予約、事前アンケートの回答、当日の面会・相性確認、里親申込書の提出、家庭訪問(ホームチェック)による飼育環境の確認、必要備品の準備、誓約書の締結、引き渡し後のフォローという段取りです。ピースワンコの公開情報でも同様のステップが示され、フォームや申請書類、必要な説明項目が案内されています。こうした段階的手続きは、里親側の生活環境・飼養計画と、個体の性質・健康状態の適合性を相互に担保するために設けられています。(参照:譲渡までの流れ)
| ステップ | 概要 | 参考リンク |
|---|---|---|
| 面会予約 | 里親希望者アンケート回答後に来場日時の調整 | 公式フロー |
| 申込書提出 | 申込書提出・身分証確認・書類審査 | 公式フロー |
| 家庭訪問 | 飼育環境の確認と飼育方法のアドバイス | 公式フロー |
| 受け入れ | 受け入れ準備の完了後に誓約書へ署名 | 公式フロー |
用語メモ:ホームチェック=家庭訪問。転落・誤飲・脱走などの事故予防観点で住環境を確認する手続き。環境エンリッチメント=知的・嗅覚的刺激や運動機会を増やし、問題行動の予防やQOLの向上を図る取り組み。マイクロチップ=個体識別用の極小IC。混合ワクチン=複数感染症に対するワクチンの総称(種類やスケジュールは獣医師判断に依存)。
譲渡判断では、犬の年齢・既往歴・気質・トレーニングの進捗、里親側の生活リズム(留守番時間、居住形態、近隣環境、同居家族の有無や年齢構成)など複数条件を合わせて総合評価します。集合住宅での飼養規約、近隣騒音、アレルギーや衛生面の配慮、万一の逸走に備えた迷子札や登録、災害時避難計画といった実務上の要素も重要です。譲渡後のフォロー(トライアル、定期連絡、相談窓口)も含めてプロセスを可視化することで、犬と里親双方にとってリスクの低いスタートが切れるよう設計されています。こうした段取りが公開されているかは、団体の説明責任や透明性を測る手がかりになります。
代表の経歴と運営体制

運営体制を理解するには、プロジェクト名と法人格、役職者の役割分担を分けて捉えるのが有効です。ピースワンコ・ジャパンは認定NPO法人が運営する事業の一つであり、理事会や監事による監督、業務執行責任者の指揮系統、現場部門(保護・医療・譲渡・広報など)のラインで構成されるのが一般的な枠組みです。代表は団体全体の戦略、コンプライアンス、資金調達方針の決定に関与し、各事業部門の責任者がオペレーション管理を担います。公開情報では、年次計画や改善計画が示され、2018年前後に指摘された運営課題を受けて、獣医師人員の強化、データ管理(接種歴・病歴・投薬歴などの個体カルテ)の標準化、犬舎の増設や動線最適化が継続的テーマとして扱われています。
非営利組織のガバナンス上、理事会は利益相反の管理、内部統制の整備、情報公開の方針を定めます。情報公開の実務では、会計報告(活動計算書・貸借対照表・財産目録など)、年次報告、活動ハイライト、主要KPI(引き取り数、譲渡数、飼育頭数の推移、医療実績、スタッフ数など)が重要な指標です。これらは、寄付者や里親希望者、地域行政、他団体との連携において、説明責任を果たすための基盤になります。とりわけ大規模収容を実施する団体では、収容密度、感染症対策、休養・運動の確保、行動管理の標準手順(SOP)、非常時対応手順(避難、停電、猛暑日の運用など)を文書化し、教育・訓練を通じて運用に落とし込むことが求められます。
評判を巡る論点の多くは、こうしたガバナンスやSOPの成熟度に帰結します。たとえば、狂犬病予防注射の遅延が生じた背景には、急増する引き取りに対する医療キャパシティと記録業務の逼迫が影響した可能性が指摘され、団体側はシステムと人員の増強、優先順位付け(トリアージ)の徹底を示しました。大規模運営では、①初動医療の優先順管理、②隔離・観察の動線管理、③データ重複入力の排除(電子カルテと現場記録の統合)、④監査可能性(いつ誰が何をしたかの追跡)を実装することが遅延リスクの低減に直結します。
運営体制を評価する視点:理事会の監督機能、内部監査や外部監査の有無、KPIの定義と公開頻度、苦情・事故の受付と改善までのPDCA、非常時の代替手順(バックアップ電源、猛暑対策、水害対策)などを資料から読み取ると、評判の背景を構造的に理解できます。
数値面では、引き取り数と譲渡数のバランス、平均在舎日数、医療関連の主要指標(接種完了率、手術件数、隔離から一般犬舎への移行率など)が、オペレーションの健全性を示す代表的KPIです。これらが明示されるほど、第三者は団体の方針・能力を客観的に評価しやすくなります。公開されている年次の要点(殺処分機停止の継続、譲渡数の増加傾向、飼育頭数の減少への転換など)は、収容密度の緩和や個体別介入の精度向上につながる要素として位置づけられます。
安倍誠の役割と発信内容
安倍誠はプロジェクトの現場運営と対外コミュニケーションの双方に関与するキーパーソンとして紹介されることが多く、役割は時期や媒体により「プロジェクトリーダー」「プロジェクトマネージャー」など表現の揺れが見られます。現場では、保護直後の評価、社会化・行動改善プログラムの策定、譲渡に向けた適合支援(里親側の生活環境と個体の特性のマッチング)など、臨床行動学やハンドリングの技能を要する領域が中心となります。公開動画や記事で示される現場説明は、犬のストレスサイン(パンティング、反復行動、回避姿勢など)への理解や、正の強化(望ましい行動に報酬を与える)を基調とするトレーニング方針を示唆することが多く、近年主流の人道的トレーニングとの親和性が高いと解釈できます。
外部発信の役割は、①活動の可視化(収容環境、運動・遊戯機会、診療・手術体制、譲渡の実際)、②誤解や懸念の解像度向上(過去の遅延の原因、改善手順の現況)、③文化的啓発(終生飼養、適正飼養、繁殖制限の重要性)に大別されます。SNSや動画は、瞬間的な拡散力が高い一方で、断片的な映像・テキストが独り歩きしやすい媒体特性があります。そのため、現場の標準手順や安全管理の説明は、短尺動画だけでなく長文記事や施設見学のガイドなど、複数フォーマットで補完されることが望まれます。肩書や役割の最新性は、公式運営のアカウントや最新のリリースで再確認するのが確実です。
行動・感情面への配慮では、犬のウェルフェア(幸福や健全な状態)を構成する「5つの自由」(飢え・渇きからの自由、不快からの自由、痛み・傷害・病気からの自由、自然な行動を表現する自由、恐怖・苦悩からの自由)が広く参照されます。現場責任者のメッセージや運用の中で、これらの自由をどう具体化しているか(例:運動・探索の機会、恐怖刺激の低減、医療への迅速アクセス)が示されると、評判に関する議論も行動科学に根差した基盤で交わされやすくなります。
専門用語の補足:正の強化=望ましい行動直後に報酬を与え再発生を促す学習原理。トリアージ=優先順位に基づく資源配分。QOL(生活の質)=行動・生理指標や環境充足度を総合した概念。これらは保護施設の運営評価でも中心的概念として用いられます。
安倍誠に関する情報を参照する際は、一次発信(公式サイト、公式SNS、公式動画)と二次情報(ニュース、インタビューの引用など)を区別し、文脈(公開日、撮影時期、肩書の更新)を併せて確認すると、情報の鮮度と正確性が担保しやすくなります。肩書が変遷する場合や、組織図が更新される場合があるため、現時点の役割は最新の一次情報での照合が推奨されます。
【ピースワンコ】評判の論点整理

- 内部告発の内容と真偽
- 杉本彩の指摘と背景
- 寄付をやめる手続きと注意点
- 闇とされる論点の検証
- 【総括】ピースワンコの評判の結論
内部告発の内容と真偽
評判に関わる最もナイーブな論点が、内部告発や週刊誌報道の扱いです。公開情報を俯瞰すると、主な論点は(1)医療・予防接種の遅延、(2)過密や行動管理の不足といった飼育環境の課題、(3)会計・広報費の比率に関する疑念、の三つに整理できます。団体側は、2018年前後の急増した引き取りへの対応の中で遅延が生じた点を認め、以降の体制強化(獣医師・スタッフの確保、カルテ管理の徹底、犬舎増設)を説明しています。報道やブログは表現や事実認定の幅が大きいため、一次資料(団体の公式発表、行政の判断・通知、統計データ)との突き合わせが不可欠です。
医療・予防接種に関しては、国レベルでは狂犬病予防法や動物の愛護及び管理に関する法律に基づく枠組みがあり、自治体の運用に沿って予防注射・登録・譲渡のプロセスが設計されます。一般論として、保護直後は隔離・観察と並行して混合ワクチンや寄生虫対策が優先され、狂犬病予防注射は生後月齢や健康状態、隔離期間の終了時期に応じてスケジュール化されます。遅延が生じた事案については、不起訴(刑罰に問わない処分)の通知が公表され、団体は改善策の実装を継続している旨を発信しています。これらは、法令遵守の枠組みの中で改善サイクルが回っているかを評価する材料になります。
| 論点 | 確認すべき一次資料 | 評価の視点 |
|---|---|---|
| 予防接種の遅延 | 公式発表、行政手続きの結果文書 | 遅延の要因分析と再発防止策の具体性 |
| 飼育環境の過密 | 施設仕様、収容頭数・面積、改善計画 | 収容密度の変化、運動・隔離環境の拡充 |
| 会計・広報費 | 年次報告・監査済み会計書類 | 費目の透明性、KPIとの整合性 |
報道は時期の偏りと見出しの強調が生じやすく、SNSは断片的な体験談が増幅される傾向があります。時系列での変化(改善の履歴)と、一次資料の有無を軸に読み解くと、真偽の判別が相対的に行いやすくなります。
全国の殺処分や引取りの実情を俯瞰する統計は、文脈理解の助けになります。たとえば、自治体による犬・猫の引取り頭数や返還・譲渡数の推移は公的統計として毎年度集計されており、民間団体の活動環境(収容需要の変動)を理解する基礎データになります。(出典:環境省 自治体における犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況)
内部告発に接した読者が最終判断に至るまでには、当時の施設規模、スタッフ体制、地域の引取り需要、法的枠組み、そして改善後のKPIを横断的に確認するプロセスが有効です。一次資料と団体の最新の説明(施設見学、公開動画、年次報告)を組み合わせることで、断片的な情報のバイアスを最小化し、より客観的な認識に近づけます。
杉本彩の指摘と背景
芸能活動と並行して動物福祉の啓発に取り組む杉本彩は、過去に各種媒体で保護活動の在り方や殺処分ゼロをめざす施策の課題について問題提起を行ってきたことで知られています。議論の焦点は、団体固有のスキャンダル追及というよりも、より普遍的な論点—すなわち「数を救うこと」と「個体のウェルフェア(福祉)」の最適な両立は可能か、という命題に置かれやすい傾向があります。広域に多数の犬を引き取るモデルは、短期的には殺処分数の抑制に寄与し得る一方、収容密度やスタッフ配置、医療・行動ケアのキャパシティといった運用面のひずみを生みやすいという構造的リスクを抱えます。杉本の発信は、この構造的リスクを社会に共有させ、制度や運営の透明性を高める方向へ議論を促す役割を果たしてきました。
とりわけ評価が分かれやすいのは「ゼロ」という目標値の提示です。可視化しやすい数値目標は社会的な合意形成に有効ですが、運用現場では個体差の大きい犬種・年齢・既往歴・気質が複雑に絡み、単純なKPIで語れない場面が多く存在します。そのため、目標値の掲示に加えて、①入退舎の基準、②医療・行動介入の優先順位、③長期在舎個体への環境エンリッチメントとQOL維持、④譲渡困難犬への終生飼養体制と資金計画、といった「過程の指標」が説明されているかどうかが、批判・擁護いずれの立場からも注視されます。杉本の問題提起は、こうした過程の指標の明文化と公開—すなわち説明責任の徹底—を強く求める文脈で理解されます。
また、情報発信のトーンと受け手の解釈ギャップにも注意が必要です。強い言葉やセンセーショナルな表現は注目を集める半面、当該団体の改善努力や最新の運用状況が十分に伝わらないリスクを伴います。よって、読者・支援者の側では、時点をそろえた一次情報(年次報告、監査報告、運営方針の更新、最新の施設動画・見学記録など)を併読し、過去の指摘が現在どのように改善・継続・未解決なのかを具体的に照合する作業が欠かせません。メディア記事やSNS投稿には、当時の状況を鋭く切り取る価値がある一方で、継時比較や全体最適の判断には、定量的データと標準手順(SOP)の開示・運用記録が必要になります。
確認のポイント:①発信日時と対象事案の時期、②一次資料(公式発表・行政資料・監査結果)の有無、③改善策が具体的手順やKPIに落ちているか、④第三者による検証(施設見学、自治体との連携文書、公開ヒアリングなど)があるか。これらを押さえると、指摘の意義と現在の実態を切り分けやすくなります。
結局のところ、杉本彩の指摘は、個別団体の賛否を超えた「大規模保護の責任」と「個体のウェルフェア」の均衡という永続的テーマを可視化する機能を持ちます。読者が判断材料を得るには、当該団体の最新の数値・運営方針・施設仕様に、第三者の評価枠組み(ウェルフェアの5つの自由、行動指標、収容密度や在舎日数の推移など)を重ねて吟味するアプローチが有効です。
寄付をやめる手続きと注意点

継続寄付の停止(いわゆる解約・退会)を検討する際に重要なのは、「どの決済手段で」「いつ申し込んだ継続課金か」をまず特定することです。クレジットカードの定期課金、口座振替、外部決済サービス経由の月額支援など、課金経路が複数ある場合、それぞれの停止窓口や締め日が異なるため、団体側の退会フォームと、決済事業者側のマイページ設定を併せて確認するのが確実です。多くの団体では、月次決済の締め日(例:毎月20日締めなど)が定められており、その期限前の申請で当月分の課金停止に間に合う—といった運用が一般的です。締め日後の申請は翌月適用となることがあるため、停止の意思決定は早めに着手するのが無難です。
寄付証明書(受領証明書)や領収書の管理も、停止時の実務で見落とされがちなポイントです。特に認定NPOへの寄付は税制優遇(所得控除または税額控除)の対象となる場合があり、確定申告に必要な書類を紛失すると控除適用が難しくなります。電子発行に対応する団体も増えているため、退会前に過去分の受領証明書の再発行方法や保存場所(メール添付、会員マイページ、郵送記録など)を確認しておくと安心です。控除方式の選択や上限額の扱いは税法の要件に依存するため、最終的な判断は一次情報(国税庁の公式解説)での確認が推奨されます。(出典:国税庁「寄附金控除」)
| 確認項目 | 押さえるポイント | リスク低減のコツ |
|---|---|---|
| 決済手段 | カード・口座・外部サービスの別を特定 | 団体フォームと決済事業者設定の両方で停止 |
| 締め日 | 当月停止の締切日時を確認 | 余裕をもって申請、記録はスクリーンショット |
| 受領証明 | 紙か電子か、再発行手順の有無 | 退会前に年度分をダウンロード・保管 |
| 控除適用 | 認定NPOか、控除方式の選択可否 | 公的解説で要件確認、確定申告の期限管理 |
| 再開可否 | 停止後の再開手順・会員特典の扱い | 将来の再支援を想定し情報を残す |
手順の要点:①退会フォームからの停止申請、②自動継続の決済側設定の停止、③受領証明の保管と控除に関する確認、④申請履歴の保存(受付メールや画面キャプチャ)をセットで行うと、二重請求や控除漏れのリスクを抑えられます。
寄付停止は、団体への不信の意思表示と受け止められがちですが、家計や支援方針の見直しなど中立的な理由も一般的です。停止にあたっては、可能であればアンケートで理由をフィードバックすると、団体側の運営改善(情報公開、報告頻度、使途の透明性向上)に資する場合があります。将来的に再開の可能性がある読者は、ニュースレターや年次報告の購読だけ継続する選択肢も検討できます。
闇とされる論点の検証
インターネット上で闇という言葉が用いられる背景には、①情報の非対称性(現場の詳細が外部から見えにくい)、②感情的な拡散(ショッキングな事例がトレンド化しやすい)、③更新遅延(過去の指摘が現在もそのままの印象で流通する)という三つの構造要因があります。これらを緩和する実務的な方法は明確で、一次資料へのアクセスと、時点をそろえた比較が基本です。団体評価においては、年次報告・会計書類・施設仕様・標準手順(SOP)・事故/苦情の受付と対応記録・KPIの推移(引取り、譲渡、在舎、手術、ワクチン完了率など)といった定量・定性的データの双方を突き合わせ、個別のトラブルと組織的傾向を分解して考える必要があります。
具体的には、(A)施設の収容密度と在舎日数の関係、(B)医療体制のキャパシティ(獣医師数、外部病院との連携、手術可能件数)、(C)行動ケアの実行度(社会化プログラムの頻度、運動・探索機会、ケージ外活動時間)、(D)情報公開の頻度と網羅性(数値の更新間隔、否定的事案の扱い)を、それぞれ年ごとに確認します。これにより、過去の負荷集中やボトルネック(たとえば記録業務の遅延、隔離室の不足、猛暑日の運用計画の不備など)が、現在では解消・軽減・未解消のいずれに位置づくかを把握できます。闇という抽象的な語に具体的な検証項目を与えることで、可視化と改善の余地が明確になります。
第三者情報の読み取りでは、見出しの強い言葉に引きずられず、本文の根拠、引用元、脚注を確認してください。匿名証言や未確認情報は手がかりになり得ますが、最終判断の根拠には一次資料が不可欠です。誤情報の拡散を避けるため、共有時には出典リンクと日時を併記するのが望ましい実務です。
議論を建設的に進めるには、批判も称賛も「改善提案」へ接続させる視点が有効です。たとえば、①犬舎の混雑時間帯に合わせた散歩・運動シフトの増員、②隔離・観察スペースの追加整備、③電子カルテのUI改善と入力簡素化、④譲渡後フォローのKPI化(連絡応答率、トライアル継続率)、⑤真夏日運用の事前公表(送風・給水・冷却マット等の標準装備)、などは、いずれの団体にも普遍的に通用する打ち手です。読者にとっては、こうした提案が団体の現行運用と照らしてどの程度実装されているかを見ることで、評判に関する印象論から一歩進んだ評価が可能になります。最終的には、数字・手順・現場記録という三つの柱に基づき、批判も支援もエビデンスドリブンで行うのが望ましい姿勢です。
【総括】ピースワンコの評判の結論
- 評判の判断には一次情報と時系列の整理が不可欠
- 内部告発や報道は出所と更新日の確認が重要
- 医療体制の強化やカルテ管理の標準化を注視
- 収容密度と在舎日数の推移で環境負荷を把握
- 避妊去勢の方針と未手術個体の管理ルールを確認
- 隔離観察とワクチンスケジュールの整合性を確認
- ドッグランや運動機会など環境エンリッチを確認
- 譲渡プロセスの透明性とホームチェックの徹底
- 譲渡後フォローの指標化と連絡体制の整備状況
- 会計開示の粒度と広報費の位置づけを確認
- 代表や責任者の役割と監督体制の明確性を確認
- 改善策の具体性と再発防止の運用記録を評価
- 見学や動画公開など現場可視化の取り組みを確認
- 寄付停止手順や受領証管理など実務情報を把握
- 闇という抽象語は検証項目で具体化して評価
- 最終判断は数値と手順と一次資料の突合で行う

