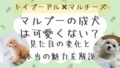マルプーを飼い始めたものの、「思っていたのと違う…」と後悔してしまう人は少なくありません。特に、マルプー 失敗と検索している人の多くは、飼いにくさや予想外の問題に直面しているのではないでしょうか。
例えば、「売れ残りのマルプーを迎えたが、社会化が不十分でなかなか馴染まない」「成犬になったら巨大化してしまい、想像以上に大きくなった」といったケースが挙げられます。また、「マルプーの問題行動は?」「落ち着きがないけど大丈夫?」といったしつけの悩みもよく聞かれます。
さらに、健康面に関する疑問も多く、「マルプーは短命?」と心配したり、「マルプーはカットしない方がいい?」と適切なケア方法に悩んだりする人もいます。体臭が気になるという声もあり、「マルプーは臭い?」と疑問を持つ飼い主も少なくありません。
加えて、無駄吠えや気性の激しさについての悩みも多く、「無駄吠えをなくすには?」「多頭飼いでもうまくいく?」といった問題に直面することもあります。マルプーは確かになぜ人気のある犬種なのか理解できるほど愛らしく賢い犬ですが、適切な飼育方法を知らないとトラブルが起こる可能性もあるのです。
この記事では、マルプー 失敗を防ぐためのポイントや、飼育における注意点について詳しく解説していきます。これからマルプーを迎える予定の人も、すでに飼っている人も、正しい知識を身につけて楽しい生活を送るための参考にしてください。
- マルプーの飼育で後悔しやすいポイントと対策
- 売れ残りのマルプーを迎える際の注意点
- マルプーのしつけや問題行動の対処法
- 健康管理やトリミングの必要性
マルプーの失敗しやすい飼い方と対策

- 売れ残りマルプーを選ぶときの注意点
- マルプーを飼って後悔しないための対策
- マルプーはなぜ人気?実際の飼いやすさとは
- 成犬になると巨大化?マルプーの成長後のサイズ
- マルプーは短命?寿命と健康管理のポイント
売れ残りマルプーを選ぶときの注意点
売れ残りのマルプーを選ぶ際には、慎重に判断することが求められます。ペットショップやブリーダーでは、生後数ヶ月以内の子犬が人気を集めやすいですが、一定の時期を過ぎると売れ残るケースもあります。価格が下がることでお得に感じるかもしれませんが、購入前に確認すべきポイントがいくつかあります。
まず、健康状態のチェックは必須です。売れ残る理由の一つとして、体調面の問題が隠れていることがあります。毛並みがパサついていないか、目や鼻に異常はないか、歩行に違和感がないかを細かく観察しましょう。また、獣医師による健康診断を受けているかを確認することも大切です。販売店によっては、ワクチン接種の履歴や遺伝病の有無についての情報を提供してくれる場合もありますので、事前に問い合わせておくと安心です。
次に、社会化の進み具合も重要なポイントです。売れ残りのマルプーは、他の犬や人と接する機会が少なかった可能性があり、警戒心が強くなっていることがあります。特に、幼少期の社会化が不足していると、成犬になってから人見知りや攻撃的な行動をとることもあります。販売店での様子を観察し、スタッフの手に対してどのような反応をするかを見極めましょう。
さらに、売れ残りの理由を必ず確認することも大切です。単に見た目の好みや毛色の違いで売れ残っているのか、それとも性格や行動面に問題があるのかを知ることで、適切な準備ができます。例えば、過去に何度も引き取り手が現れたが返されてしまったというケースでは、問題行動の可能性も考えられます。そのため、販売スタッフに「この子が売れ残っている理由は何か」「過去にどのような生活を送っていたのか」を具体的に聞くようにしましょう。
最後に、飼育環境が適切かどうかも確認しておくべき点です。劣悪な環境で育った犬は、病気のリスクが高く、しつけが難しいことがあります。ペットショップの場合はケージの衛生状態、ブリーダーの場合は飼育環境全体をチェックし、安心して迎えられるかを見極めることが必要です。
このように、売れ残りのマルプーを選ぶ際には、健康状態・社会化・売れ残った理由・飼育環境の4点をしっかり確認することで、後悔のない選択ができます。慎重に判断し、新しい家族として迎える準備を整えましょう。
マルプーを飼って後悔しないための対策

マルプーを迎え入れたものの、思っていたより大変で後悔してしまう飼い主も少なくありません。しかし、事前にしっかりと準備をし、適切な対策を講じることで、快適な生活を送ることができます。ここでは、特に注意すべきポイントについて解説します。
まず、飼育にかかる費用を理解しておくことが大切です。マルプーは小型犬ですが、定期的なトリミングが必要なため、維持費が想像以上にかかることがあります。トリミングは1〜2ヶ月に1回の頻度で行う必要があり、1回あたり5,000円〜10,000円程度かかることが一般的です。さらに、ワクチン接種や健康診断、フード代などの費用も発生します。これらを踏まえ、年間の飼育コストを把握し、無理なく維持できるかを考えることが重要です。
次に、マルプーの性格を理解し、しつけの重要性を認識する必要があります。マルプーは賢く愛嬌のある犬ですが、甘えん坊で分離不安になりやすい一面があります。長時間の留守番が苦手なため、仕事などで外出時間が長い家庭ではストレスを溜めやすくなります。こうした問題を防ぐためには、飼い主がいない時間でも安心して過ごせる環境を整えることが大切です。例えば、おもちゃや知育玩具を活用することで、寂しさを紛らわせる工夫をするとよいでしょう。
また、無駄吠えや問題行動を防ぐために、早期のしつけを徹底することも不可欠です。マルプーは警戒心が強い個体も多く、適切な社会化ができていないと、吠え癖がついてしまうことがあります。来客時や外出時に無駄吠えをしないよう、「待て」「お座り」などの基本的なしつけをしっかりと行い、落ち着いて行動できるように訓練しましょう。
最後に、マルプーは体調管理にも気を配る必要があります。特に、膝蓋骨脱臼(パテラ)や涙やけなどの症状が出やすいため、日々の健康チェックを怠らないことが大切です。適度な運動とバランスの取れた食事を意識し、健康を維持できるような環境を整えましょう。
これらの対策を事前にしっかりと講じることで、マルプーを飼って後悔するリスクを減らすことができます。可愛さだけに惹かれるのではなく、長く一緒に暮らすパートナーとして、適切な準備を整えて迎え入れましょう。
汚かった愛犬の涙やけをキレイにする獣医も薦める犬の涙やけ対策「涙やけクリア」 ![]()
マルプーはなぜ人気?実際の飼いやすさとは
マルプーは、その愛らしい見た目と賢い性格から非常に人気のある犬種です。しかし、単に「可愛い」という理由だけではなく、飼いやすさの面でも多くの飼い主から支持されています。ここでは、マルプーの人気の理由と、実際の飼育のしやすさについて詳しく解説します。
まず、人気の最大の要因は、その見た目の魅力にあります。マルチーズとトイプードルのミックス犬であるため、フワフワとした毛並みと丸い瞳が特徴的です。また、成犬になってもコンパクトな体型を維持しやすく、小型犬ならではの可愛らしさが続くことも人気の理由の一つです。
次に、抜け毛が少なく、アレルギー体質の人でも比較的飼いやすいという点もメリットとして挙げられます。トイプードルの血統を受け継いでいるため、毛が抜けにくく、室内の掃除がしやすいのが特徴です。ただし、毛が伸び続けるため、定期的なトリミングが必要となります。
一方で、実際に飼育する際には注意すべき点もあります。マルプーは非常に賢い犬種ですが、甘えん坊な性格も持ち合わせているため、分離不安を起こしやすい傾向があります。そのため、長時間の留守番が続く環境には向いていません。また、社交性が不足していると警戒心が強くなり、吠えやすくなることもあります。
このように、マルプーは人気の理由が多い一方で、適切なしつけやケアが必要な犬種でもあります。飼い主としての責任を理解し、愛情を持って育てることが重要です。
成犬になると巨大化?マルプーの成長後のサイズ

マルプーを迎えようと考えている人の中には、「成犬になったら予想以上に大きくなるのでは?」と心配する人もいるでしょう。一般的に、マルプーの成犬時の体重は3〜6kg程度、体高は25〜30cmほどが平均ですが、個体差が大きいため、成長後のサイズを完全に予測するのは難しいとされています。
マルプーのサイズが予測しづらい最大の理由は、親犬であるマルチーズとトイプードルの遺伝的要因が関係しているためです。マルチーズは体重2〜4kg程度、トイプードルは2.5〜4kgが標準とされていますが、トイプードルの血統によっては、ミニチュアプードルの遺伝を受け継ぐこともあり、予想よりも大きくなる可能性があります。そのため、成長後のサイズを気にする場合は、親犬の体格を事前に確認することが重要です。
また、成長の過程での食事や運動量も体の大きさに影響を与えます。例えば、子犬の頃に高カロリーの食事を与えすぎると、肥満気味になり、標準サイズよりも大きくなることがあります。一方で、適度な運動を取り入れ、バランスの良い食事を与えることで、理想的なサイズに成長する可能性が高まります。
成犬になってからも、体重管理には注意が必要です。特にマルプーは、体型が崩れると関節や心臓に負担がかかるため、適切な運動習慣を持たせることが大切です。成長期を過ぎても急激に体重が増えるようであれば、獣医師に相談し、食事内容の見直しや適切な運動方法を考えるのがよいでしょう。
マルプーが「巨大化する」と感じるケースの多くは、期待していたサイズよりも成犬時の体格が大きくなった場合に起こります。しかし、事前に親犬の特徴を知り、適切な食事や運動を取り入れることで、成犬になったときのギャップを最小限に抑えることができます。
マルプーは短命?寿命と健康管理のポイント
マルプーの平均寿命は12〜15年程度とされています。これは小型犬の一般的な寿命とほぼ同じであり、決して短命とは言えません。しかし、遺伝的要因や健康管理の仕方によっては、寿命が短くなる可能性もあるため、適切なケアを心がけることが重要です。
マルプーの寿命に影響を与える要因の一つとして、遺伝的な病気が挙げられます。マルチーズとトイプードルの両方が遺伝的にかかりやすい病気を持っている場合、マルプーにもそのリスクが引き継がれることがあります。特に、膝蓋骨脱臼(パテラ)、気管虚脱、白内障、アレルギーなどは注意が必要な疾患です。これらの病気は、日頃のケアや早期発見によってリスクを軽減することが可能です。
健康管理のポイントとして、まずは食事に気を配ることが重要です。栄養バランスの良いフードを与え、肥満を防ぐことで、関節や内臓の負担を軽減できます。また、ドッグフードの質も重要で、添加物の多いフードよりも、高品質な原材料を使用したものを選ぶとよいでしょう。
次に、適度な運動を取り入れることも欠かせません。マルプーは小型犬ですが、活発で遊び好きな性格を持っているため、適切な運動量を確保することでストレスを軽減し、健康を維持できます。ただし、激しい運動は関節に負担をかけるため、散歩や軽めの遊びを取り入れることが推奨されます。
さらに、定期的な健康診断を受けることも大切です。特に高齢になると、見た目ではわかりにくい内臓の病気が進行することもあるため、年に1〜2回の健康診断を受けることで早期発見・早期治療につなげることができます。
マルプーは特別短命な犬種ではありませんが、長生きさせるためには日頃のケアが重要です。適切な食事管理、運動習慣、定期的な健康診断を行うことで、愛犬とより長く健康的な生活を送ることができるでしょう。
マルプーの失敗を防ぐしつけとケアのコツ

- マルプーはカットしない方がいい?お手入れの基本
- マルプーの臭い対策!体臭の原因と解決法
- 無駄吠えをなくすには?正しいしつけ方法
- マルプーのしつけが難しい理由と解決策
- 多頭飼いで失敗しないための注意点
マルプーはカットしない方がいい?お手入れの基本
マルプーを飼う際、「カットしない方がいいのか?」と疑問に思う飼い主も多いですが、結論から言えば、マルプーの毛は定期的なカットが必要です。マルチーズとトイプードルの特徴を受け継ぐため、伸び続ける毛質の個体が多く、放置すると毛玉や皮膚トラブルの原因になることがあります。
特に、マルプーの毛質は個体差が大きく、直毛に近いタイプ、ゆるくウェーブがかった毛、しっかりカールしている毛など、様々なパターンが存在します。そのため、毛の伸び方によって適切なトリミングの頻度を決めることが大切です。一般的には1〜2ヶ月に1回のトリミングが推奨されています。
カットをしない場合、毛が伸びすぎて視界を妨げたり、耳の中が蒸れて炎症を起こしたりすることがあります。特に目の周りの毛は、伸びすぎると涙やけの原因にもなるため、定期的にカットすることが望ましいです。また、毛玉ができるとブラッシングでは解消できない場合があり、皮膚を傷つける恐れがあります。
お手入れの基本として、ブラッシングは毎日行うのが理想です。毛が絡まりやすい犬種のため、専用のスリッカーブラシを使い、優しくブラッシングすることで毛玉の予防になります。また、シャンプーは月に1回程度を目安に行い、皮膚の健康を維持することが重要です。
さらに、耳掃除や爪切り、歯磨きなども定期的に行うことが大切です。特に耳の中は湿気がこもりやすく、放置すると外耳炎のリスクが高まります。獣医師のアドバイスを受けながら、正しいケア方法を習得するとよいでしょう。
このように、マルプーの毛は放置するとさまざまな健康トラブルの原因になるため、適切なカットとお手入れが必要です。見た目を整えるだけでなく、愛犬の健康を守るためにも、日頃のケアをしっかりと行いましょう。
この投稿をInstagramで見る
マルプーの臭い対策!体臭の原因と解決法
マルプーを飼っていると、「思っていたよりも臭いが気になる」と感じることがあるかもしれません。犬種として特別体臭が強いわけではありませんが、飼い方やケアの方法によって臭いが発生することがあります。臭いの原因を理解し、適切な対策を取ることで、快適な環境を維持することができます。
まず、マルプーの体臭の主な原因には、皮脂の分泌、耳の汚れ、口臭、肛門腺の分泌物、食事の影響などが挙げられます。犬の皮膚には皮脂腺があり、そこから分泌される皮脂が酸化すると独特の臭いを発することがあります。特に、シャンプーの頻度が少なすぎたり、換毛期に適切なブラッシングをしなかったりすると、皮脂が溜まって臭いが強くなることがあります。
また、耳の汚れも臭いの原因になります。マルプーは耳が垂れているため、耳の中が蒸れやすく、雑菌が繁殖しやすい環境になっています。そのため、耳の掃除を怠ると、悪臭の原因となることがあります。特に、耳をしきりに掻いたり、頭を振る仕草が多い場合は、耳垢の蓄積や外耳炎を疑う必要があります。
口臭も飼い主が気になる臭いの一つです。歯石が溜まることで口の中に細菌が増え、強い臭いを発することがあります。特に、ドライフードよりもウェットフードを多く与えている場合や、歯磨きを習慣化していない場合は、口臭が強くなる傾向があります。
これらの臭いを解決するためには、適切なケアが不可欠です。まず、シャンプーは月に1〜2回の頻度で行い、皮脂の酸化を防ぐことが重要です。ただし、洗いすぎると皮脂の分泌が過剰になり、逆に臭いが強くなることがあるため、適度な頻度を保ちましょう。また、日常的なブラッシングを行うことで、汚れや抜け毛を取り除き、臭いの原因を減らすことができます。
耳のケアも大切です。週に1回程度、専用のイヤークリーナーを使って優しく拭き取ることで、耳の中の清潔を保つことができます。過剰な掃除は逆効果になることもあるため、適度に行うことがポイントです。
口臭対策としては、毎日の歯磨きを習慣化するのが最も効果的です。犬用の歯磨き粉やデンタルガムを活用し、歯石の蓄積を防ぐことで、口臭を抑えることができます。
このように、マルプーの臭いは適切なケアによって軽減することができます。臭いが強くなった場合は、健康上の問題が隠れていることもあるため、定期的に獣医師の診察を受けることも忘れずに行いましょう。
無駄吠えをなくすには?正しいしつけ方法
マルプーは賢く飼い主に忠実な犬種ですが、警戒心が強い子が多いため、無駄吠えの問題に悩む飼い主も少なくありません。特に、来客時や外の物音に反応して吠えることが多く、マンションや集合住宅では近隣トラブルにつながる可能性もあります。無駄吠えを防ぐには、正しいしつけと環境の調整が必要です。
無駄吠えの原因としては、警戒心、不安、要求吠え、退屈によるストレスなどが考えられます。例えば、来客時に吠えるのは「知らない人が来た」という警戒心からくる行動ですし、飼い主にかまってほしくて吠える場合は、要求吠えになります。それぞれの原因に応じた適切なしつけを行うことが大切です。
まず、警戒心からくる無駄吠えを防ぐには、社会化を進めることが重要です。子犬のうちからさまざまな人や環境に慣れさせることで、不必要に警戒しなくなります。また、来客時にはおやつを使って「吠えなければご褒美がもらえる」という学習を促すと、無駄吠えが減ることがあります。
要求吠えの場合は、吠えたときにすぐに反応しないことがポイントです。例えば、「おやつが欲しい」「遊んでほしい」といった理由で吠えたときに、飼い主がすぐに応じてしまうと、「吠えれば願いが叶う」と学習してしまいます。そのため、吠えても無視し、静かになったときに褒めるようにすると、徐々に吠え癖が改善されます。
環境の調整も無駄吠え対策の一つです。窓の外の音や人の気配に反応して吠える場合は、カーテンを閉めたり、ホワイトノイズを流すなどして刺激を減らすと良いでしょう。また、十分な運動をさせることでエネルギーを発散し、ストレスによる無駄吠えを防ぐこともできます。
このように、無駄吠えの原因を特定し、適切なしつけと環境調整を行うことで、マルプーの無駄吠えを減らすことができます。焦らず、根気よくトレーニングを続けることが大切です。
マルプーのしつけが難しい理由と解決策
マルプーは賢い犬種ですが、その反面、しつけが難しいと感じる飼い主も少なくありません。特に、頑固な性格や甘えん坊な一面が影響し、思うようにトレーニングが進まないことがあります。しつけが難しいとされる理由を理解し、適切な対応をすることで、よりスムーズにしつけを進めることができます。
マルプーのしつけが難しい理由の一つは、個体差が大きいことです。マルチーズ寄りの性格の子は甘えん坊で飼い主にべったりする傾向があり、分離不安を起こしやすいです。一方で、トイプードル寄りの子は非常に賢く、飼い主の態度を敏感に察知します。そのため、一貫性のないしつけをすると、混乱してしまうことがあります。
また、自己主張が強い個体も多く、指示を無視したり、自分のルールで行動しようとすることがあります。この場合、飼い主が主導権を握り、しつけのルールを明確にすることが重要です。「ダメなことはダメ」と一貫した態度で接し、成功したときにはしっかりと褒めることで、正しい行動を定着させることができます。
さらに、飼い主が過保護になりすぎると、しつけが難しくなることもあります。甘やかしすぎず、適切な距離感を持って接することが、しつけ成功の鍵となります。
このように、マルプーのしつけには根気と一貫性が求められます。正しい方法を続けることで、良い関係を築くことができるでしょう。
多頭飼いで失敗しないための注意点

マルプーをすでに飼っている、もしくは新たに迎えたいと考えている人の中には、多頭飼いを検討している人もいるでしょう。しかし、多頭飼いは単独飼いとは異なり、慎重な準備と適切な対応が必要です。失敗しないためには、環境の整備や相性の見極め、しつけの工夫が重要になります。
まず、犬同士の相性を事前に確認することが最も大切です。すでに1匹のマルプーを飼っている場合、新しい犬を迎える前に、性格の相性をしっかりと見極める必要があります。例えば、先住犬が臆病で警戒心が強い性格の場合、新しく迎える犬が活発で好奇心旺盛なタイプだと、トラブルになりやすいことがあります。そのため、可能であればブリーダーや保護施設で何度か対面させ、反応を確認するのが理想です。
次に、犬それぞれに安心できる個別のスペースを用意することも欠かせません。多頭飼いでは、寝床や食事スペースを共有するのが理想的と思われがちですが、実際にはそれぞれの犬が自分だけの落ち着ける空間を持つことが重要です。特に、食事中に縄張り意識が強く出る犬もいるため、食器は離れた場所に配置し、同時に与えるようにしましょう。また、クレートやサークルを活用し、それぞれがリラックスできるスペースを作ることが、多頭飼いのストレスを軽減するポイントとなります。
また、しつけの方法にも工夫が必要です。多頭飼いでは、一方の犬が正しくしつけられていても、もう一方の犬が問題行動を起こすと、それに引きずられてしまうケースがあります。そのため、それぞれの犬に対して個別にトレーニングを行う時間を確保することが望ましいです。例えば、先住犬に落ち着いた行動を学ばせるために、一時的に新しい犬を別室に移してしつけを行うことも有効です。
さらに、多頭飼いは費用面の負担も増えることを理解しておくべきです。犬の頭数が増えると、フードや医療費、トリミング費用などのランニングコストが倍増します。特に、マルプーは定期的なトリミングが必要な犬種のため、多頭飼いをする場合は経済的な負担も考慮しなければなりません。事前に必要な費用をシミュレーションし、無理のない範囲で計画を立てることが大切です。
最後に、飼い主が一貫したルールを持つことも、多頭飼い成功の鍵となります。例えば、先住犬を優先するのか、新入りの犬を優先するのか、しつけのルールはどうするのかを事前に決めておかないと、犬同士の争いを招くことになります。人間の家族全員が同じルールを守ることで、犬たちも混乱せずに過ごしやすくなるでしょう。
このように、多頭飼いは単独飼いと比べて気をつけるべきポイントが多くなります。しかし、環境を整え、犬同士の関係を慎重に築くことで、互いに良い影響を与えながら、楽しく暮らしていくことができます。失敗を防ぐためにも、計画的に準備を進めることが大切です。
マルプーの飼育で失敗しないためのポイント

- 売れ残りのマルプーは健康状態や社会化の進み具合を確認する
- マルプーを飼う前に飼育コストを把握し、無理のない計画を立てる
- トリミングが必要な犬種であり、定期的なカットが欠かせない
- マルプーは甘えん坊な性格のため、分離不安になりやすい
- 成犬時のサイズは個体差が大きく、親犬の体格を参考にする
- 無駄吠えを防ぐには、社会化と一貫したしつけが重要
- マルプーの体臭は皮脂の分泌や耳の汚れが主な原因となる
- 膝蓋骨脱臼や涙やけなど、遺伝的な病気に注意が必要
- マルプーの寿命は12〜15年程度で、適切な健康管理が重要
- しつけの難易度は個体差があり、甘やかしすぎに注意する
- 食事管理を徹底し、肥満による健康リスクを防ぐ
- 長時間の留守番はストレスになりやすく、環境を工夫する
- 多頭飼いをする際は、犬同士の相性や個別のスペースを確保する
- 運動不足が問題行動につながるため、適度な運動を取り入れる
- 早期のしつけと適切なケアを行うことで、飼育の失敗を防ぐ
まとめ
マルプーを飼う際に失敗しやすいポイントと、その対策について詳しく解説しました。以下の点を押さえることで、マルプーとの生活をより快適にすることができます。
- 売れ残りのマルプーを選ぶときは慎重に
健康状態や社会化の進み具合を確認し、売れ残りの理由を事前に把握することが重要です。
- 飼育のコストやしつけの難しさを理解する
トリミング費用や医療費がかかることを考慮し、無駄吠えや問題行動に適切な対応を取ることが必要です。
- マルプーの成長後のサイズや寿命について正しく知る
個体差によって成犬時の大きさが異なり、健康管理を怠ると寿命が縮まる可能性もあります。
- 毛のお手入れや臭い対策を徹底する
カットを怠ると毛玉や皮膚トラブルの原因に。ブラッシングやシャンプー、耳掃除、歯磨きをこまめに行いましょう。
- 多頭飼いを検討するなら事前準備が重要
先住犬との相性や生活環境を整え、一匹ずつ適切なしつけを行うことが成功の鍵です。
マルプーは見た目の可愛さだけでなく、しつけやお手入れにも手間がかかる犬種です。しかし、正しい知識と準備があれば、後悔せずに楽しいペットライフを送ることができます。愛犬と幸せな時間を過ごすために、今回の内容をぜひ参考にしてください。
参考:栃木県動物愛護指導センター