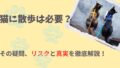猫の多頭飼いについて調べていると、「猫 多頭飼い 頭おかしい」といったキーワードを目にすることがあります。これは、多頭飼いをする人の心理や適正な頭数を理解せずに無計画に猫を迎え入れた結果、管理ができなくなり、トラブルを抱えてしまうケースが少なくないためです。では、猫を多頭飼いする場合、何匹までが理想的なのでしょうか?また、一軒家であれば何匹まで飼えるのでしょうか?
多頭飼育崩壊になってしまう飼い主の特徴として、計画性がないことや、精神疾患を抱えていることが挙げられます。特に、猫を増やしすぎてしまうと、経済的な負担やトイレの数の不足、猫同士の相性の問題が発生し、ストレスを抱えることになります。その結果、飼い主自身も後悔することになり、最悪の場合、適切な飼育が困難になることもあります。
この記事では、「猫は一匹と二匹どっちが幸せなのか」「猫を多頭飼いする場合、何匹がベストなのか」「多頭飼育崩壊を防ぐためにはどうすればいいのか」といった疑問について詳しく解説します。また、多頭飼養届出書の必要性や部屋数と飼育頭数の関係についても触れながら、後悔しないための適正な飼い方を紹介します。猫と快適に暮らすためのヒントを知り、多頭飼いを成功させましょう。
- 猫を多頭飼いする人の心理や背景を理解できる
- 適正な飼育頭数や一軒家での限界を知ることができる
- 多頭飼育崩壊のリスクや注意点を学べる
- 猫同士の相性や快適な飼育環境の作り方を理解できる
猫の多頭飼いは頭がおかしい?後悔しないためのポイント

- 猫を多頭飼いする人の心理とは?
- 猫を多頭飼いする場合は何匹がベスト?
- 猫は一匹と二匹どっちが幸せ?
- 一軒家で猫を何匹まで飼えますか?
- 多頭飼育崩壊とは?そのリスクと実例
- 多頭飼育崩壊になってしまう飼い主の特徴は?
- 猫の相性が悪いとどうなる?注意点を解説
猫を多頭飼いする人の心理とは?
猫を多頭飼いする人の心理には、さまざまな要因が関係しています。単に猫が好きで増やしているだけではなく、そこには心理的な背景や生活環境の影響が含まれることが多いです。
例えば、猫の多頭飼いをする人の中には「猫が寂しくないように」という思いから複数匹を迎える人もいます。特に、仕事や外出が多い家庭では、猫が一匹だと退屈したり孤独を感じるのではないかと考え、仲間を作ることで安心させようとするケースがあります。また、猫同士が遊んだり、グルーミングをし合ったりする姿を見て癒されるという点も、多頭飼いをする理由の一つとなります。
一方で、保護意識の強い人は、捨て猫や野良猫を見つけると放っておけずに次々と引き取る傾向があります。このような人は、動物愛護の精神から「この子を助けなければ」と強く思い、気づけば複数の猫を飼育していることがあります。特に、保護活動をしている人にとって、多頭飼いは自然な流れになりやすいです。
また、心理的な背景として「孤独感を埋めたい」という気持ちも影響しています。特に、一人暮らしの人や高齢者の中には、猫と暮らすことで心の支えを得ているケースが少なくありません。猫は無条件の愛情を注いでくれる存在であり、話し相手がいない人にとっては、精神的な安定をもたらす大切な存在になります。そのため、より多くの猫と暮らすことで、癒しや安心感を求めることもあるのです。
しかし、計画性のないまま猫の数が増えると、経済的・環境的な負担が大きくなります。猫の食費や医療費が増え、世話の手間もかかるため、適切な管理ができなくなるリスクが高まります。特に、精神的な問題を抱えている人が多頭飼いをする場合、無計画に増やしてしまうことで「多頭飼育崩壊」につながることもあります。
このように、猫の多頭飼いにはさまざまな心理的要因が影響しており、純粋な愛情だけでなく、社会的・精神的な側面も関係しているのです。そのため、猫を増やす際は、自分の生活環境や経済状況を冷静に判断し、無理のない範囲で飼育することが大切です。
猫を多頭飼いする場合は何匹がベスト?

猫を多頭飼いする場合、最適な頭数は飼い主の生活環境や猫同士の相性によって異なります。単に「広い家なら何匹でも飼える」と考えるのは危険で、猫の性格や管理のしやすさを考慮することが重要です。
一般的には、1LDKのマンションであれば1~2匹、2LDK以上の住居なら3~4匹が快適に暮らせる目安とされています。これには理由があり、猫は縄張り意識が強い動物であるため、狭い空間に多くの猫がいるとストレスを感じやすくなるためです。十分なスペースが確保できないと、猫同士のケンカが増えたり、トイレの管理が難しくなったりすることもあります。
また、猫のトイレの数も重要なポイントです。基本的に「猫の数+1個」のトイレを用意するのが望ましいとされています。例えば、3匹の猫を飼う場合は4つのトイレが必要になります。トイレの数が不足すると、猫が排泄を我慢してしまったり、トイレを巡って争いが起こったりする可能性があります。そのため、スペースや衛生管理の面からも、適切な飼育頭数を決めることが大切です。
また、多頭飼いをする際には、猫同士の相性がとても重要になります。もともと一匹で過ごすことに慣れている猫に新しい猫を迎えると、強いストレスを感じることがあります。逆に、子猫の頃から一緒に育った猫同士であれば、比較的スムーズに共存できることが多いです。そのため、飼い主は猫の性格をよく見極め、慎重に頭数を増やしていく必要があります。
加えて、経済的な負担も無視できません。猫の飼育費用は、食費や医療費、トイレ用品などを含めると1匹あたり年間10万円以上かかることもあります。複数匹飼う場合、それに比例してコストが増えるため、しっかりと資金計画を立てることが重要です。
このように、猫の多頭飼いにおいて「何匹がベストか」は、単に家の広さだけでなく、猫の性格や相性、飼い主の経済力、管理能力などを総合的に判断する必要があります。無理のない範囲で適正な頭数を決めることが、猫と飼い主双方の幸福につながるのです。
猫は一匹と二匹どっちが幸せ?
猫が一匹でいる方が幸せなのか、それとも二匹でいる方が幸せなのかは、猫の性格や生活環境によって異なります。単純に「猫は仲間がいたほうがいい」と考えるのではなく、それぞれのメリット・デメリットを考慮することが重要です。
一匹で飼う場合のメリットとしては、猫が飼い主との絆を深めやすいことが挙げられます。特に甘えん坊な猫は、他の猫と一緒にいるよりも飼い主にべったりと甘えたい性格のことが多く、一匹飼いの方が精神的に安定する場合があります。また、一匹ならトイレの管理や食事の好みの調整がしやすく、健康管理も比較的容易です。一方で、飼い主が外出している時間が長い場合、猫が寂しさを感じたり、退屈から問題行動を起こすこともあります。
二匹で飼うメリットは、猫同士が遊び相手になり、運動不足やストレスの軽減につながることです。特に、兄弟猫や幼い頃から一緒に育った猫同士であれば、自然と寄り添いながら暮らせるため、社会性が養われるメリットもあります。また、飼い主が不在の時間が長くても、猫同士で遊ぶことができるため、孤独を感じにくくなります。
しかし、二匹以上になると、猫同士の相性が悪い場合にトラブルが起こる可能性があります。特に、縄張り意識が強い猫は、新しい猫を受け入れられず、ストレスを感じてしまうことがあります。そのため、多頭飼いを考える際は、猫の性格や相性を慎重に見極めることが大切です。
結局のところ、猫の幸せは「一匹か二匹か」という単純な問題ではなく、それぞれの性格や環境に合わせて適切な飼育方法を選ぶことが重要なのです。
一軒家で猫を何匹まで飼えますか?
一軒家で飼える猫の数は、単純に「家が広いから何匹でもOK」というわけではありません。猫の生活環境や飼い主の管理能力が大きく影響します。一般的に、飼える猫の頭数を決める要素として「スペース」「トイレの数」「猫の相性」「経済的負担」の4つが挙げられます。
まず、スペースについて考えると、猫は縄張りを大切にする動物であり、十分なスペースが確保されていないとストレスを感じることがあります。一匹の猫が快適に過ごすためには、少なくとも1.8平方メートル以上の個別スペースが必要とされています。例えば、3LDKの一軒家であれば3~4匹、より広い家であれば6匹以上の飼育も可能ですが、猫同士が快適に過ごせるよう、十分な部屋数とキャットタワーなどの縦の空間を確保することが重要です。
次に、トイレの数です。猫は非常に清潔好きな動物であり、トイレが汚れていると排泄を我慢してしまうことがあります。そのため、「猫の数+1個」のトイレを設置することが推奨されています。例えば、5匹の猫を飼う場合は6個以上のトイレが必要です。また、トイレの配置も重要で、猫同士が鉢合わせしないように分散して設置すると安心して使用できます。
猫の相性も多頭飼いを成功させるための重要なポイントです。相性が悪い猫同士を無理に同居させると、ケンカが頻発したり、一方の猫が萎縮してしまったりすることがあります。そのため、新しい猫を迎える際には、既存の猫との相性を慎重に見極めることが必要です。特に、成猫同士の場合は、初対面の段階から慎重に慣れさせる工夫が求められます。
また、経済的な負担も無視できません。猫の飼育には、食費やトイレ用品、医療費などがかかります。例えば、一匹あたりの年間飼育費用は約10万~20万円とされており、5匹飼う場合は年間50万~100万円の費用がかかる計算になります。多頭飼いをする場合は、経済的に無理のない範囲で計画的に飼うことが大切です。
一軒家で猫を何匹まで飼えるかという問いに対する明確な上限はありませんが、スペース・トイレの数・猫の相性・経済的負担などを考慮したうえで、自分が責任を持って管理できる範囲内で飼育することが最も重要です。
多頭飼育崩壊とは?そのリスクと実例
多頭飼育崩壊とは、飼い主が管理できる範囲を超えて過剰に猫を飼い続けた結果、適切な世話ができなくなり、猫たちの健康や生活環境が著しく悪化する状態を指します。この問題は、単に「猫が多い」というだけではなく、猫の福祉を無視した結果、猫にも飼い主にも深刻な影響を及ぼすことが特徴です。
多頭飼育崩壊のリスクの一つは、衛生環境の悪化です。猫の数が増えるとトイレの掃除が追いつかなくなり、排泄物が放置されたままになることがあります。その結果、悪臭が発生し、住環境そのものが不衛生になります。さらに、掃除が行き届かないことで、カビや害虫が発生しやすくなり、飼い主自身の健康にも悪影響を及ぼすことがあります。
また、猫の健康管理が困難になることも大きな問題です。猫の数が多すぎると、個々の体調変化に気づきにくくなります。例えば、下痢や嘔吐が見られても、どの猫の症状なのか特定できないことが多く、病気が進行するまで気づかないケースもあります。特に、感染症が発生した場合、狭い空間で多くの猫が生活していると瞬く間に広がってしまい、適切な医療を受ける前に重症化してしまうことがあります。
さらに、経済的負担が増大することも無視できません。猫の食費、トイレ用品、医療費は、頭数が増えるほど比例して増加します。最初は問題なく世話ができていても、急な病気や手術が必要になった際、金銭的に対応できないというケースも珍しくありません。その結果、適切な医療を受けさせることができず、猫の健康状態が悪化することになります。
実例として、日本国内でも多頭飼育崩壊のケースがたびたび報道されています。例えば、愛知県では、ブリーダーが管理しきれない数の猫を飼育し続けた結果、250匹以上の猫が劣悪な環境に置かれた事例がありました。また、個人宅でも、高齢の飼い主が数匹の猫を飼い始めたものの、不妊去勢手術をしなかったために爆発的に増えてしまい、最終的に手がつけられなくなったケースもあります。こうした事例では、行政や動物愛護団体が介入し、猫たちは保護されましたが、救済されるまでに多くの猫が病気や栄養失調に陥っていました。
多頭飼育崩壊は、決して他人事ではありません。猫を迎える際は、自分の管理能力や経済的な余裕をしっかりと考慮し、無理のない範囲で責任を持って飼育することが大切です。計画的に飼うことができれば、多頭飼いは猫にとっても飼い主にとっても幸せな環境になります。
多頭飼育崩壊になってしまう飼い主の特徴は?
多頭飼育崩壊とは、飼い主が適切な管理ができなくなり、猫の健康や生活環境が著しく悪化する状態を指します。元々は猫を大切に思っていた飼い主でも、気づかないうちに飼育が破綻してしまうケースが少なくありません。そのため、多頭飼育崩壊を防ぐためには、どのような人が陥りやすいのかを知っておくことが重要です。
まず、計画性のないまま猫を増やしてしまう人は、多頭飼育崩壊になりやすい傾向があります。「かわいそうだから」「助けたいから」という思いだけで次々と猫を迎え入れると、気づいたときには管理が追いつかなくなっていることがあります。特に、保護活動をしている人や野良猫に餌をあげている人は、不妊去勢手術を怠ると短期間で猫の数が急増してしまう可能性があるため注意が必要です。
また、精神的な問題を抱えている人も、多頭飼育崩壊に陥りやすい傾向があります。環境省の調査によると、多頭飼育崩壊を起こした飼い主の約6割が高齢女性で、その多くが孤独感や精神的な不安を抱えていたことが指摘されています。猫を飼うことで癒しを得ていたものの、次第に管理が困難になり、気づけば自分の生活すらままならない状況になっていたというケースもあります。
経済的な問題も大きな要因の一つです。猫の飼育費用が増えても、それに見合った収入がない場合、必要な医療を受けさせることができなかったり、十分な食事を与えられなかったりすることがあります。特に、高齢者や低所得者層の人が猫を増やしすぎると、生活が破綻しやすくなります。
さらに、猫の健康管理ができない人も危険です。多頭飼育では、一匹ごとの体調を細かく観察することが難しくなります。特に、トイレの管理が行き届かず、病気の兆候を見逃すケースが多くなります。病気が蔓延すると治療が追いつかず、感染症の拡大を引き起こす危険性もあります。
このように、多頭飼育崩壊は誰にでも起こりうる問題です。猫を増やす前に、自分の生活環境や経済状況、健康管理の能力をしっかり見直し、無理のない範囲で飼育することが求められます。
猫の相性が悪いとどうなる?注意点を解説

猫の多頭飼いを考える際、最も重要なのが猫同士の相性です。相性が悪い猫同士を同じ空間で飼うと、さまざまな問題が発生し、飼い主にも猫にも大きなストレスを与えてしまいます。
まず、相性が悪い猫同士がいると、ケンカが頻発する可能性があります。猫同士の小競り合いはよくあることですが、本気で威嚇し合ったり、噛みついたりする場合は深刻です。特に、縄張り意識が強い猫や神経質な性格の猫は、新しい猫を受け入れにくい傾向があります。
また、相性が悪い猫同士がいると、ストレスによって体調を崩すこともあります。過度なストレスは、食欲不振や下痢、毛づくろいのしすぎによる脱毛などの症状を引き起こすことがあります。場合によっては、免疫力が低下し、病気にかかりやすくなることもあります。
猫同士の相性を見極めるためには、初対面の際に慎重に慣れさせることが重要です。最初は別々の部屋で飼育し、徐々にお互いの存在に慣れさせるのが効果的です。また、新しい猫を迎え入れる際は、先住猫と性格が合いそうかどうかを事前に確認し、慎重に選ぶようにしましょう。
このように、猫の相性は多頭飼いを成功させる上で欠かせない要素です。適切な対応を行い、猫たちが快適に過ごせる環境を整えることが大切です。
猫の多頭飼いは何匹まで?崩壊を防ぐ飼育管理

- トイレの数は何個必要?快適な環境の作り方
- 部屋数と飼育頭数の関係とは?
- 多頭飼養届出書の義務と地域ごとのルール
- 猫の多頭飼いと精神疾患の関連性とは?
トイレの数は何個必要?快適な環境の作り方
猫の多頭飼いにおいて、トイレの数は非常に重要な要素です。適切な数のトイレを設置しないと、猫がストレスを感じたり、排泄を我慢することで健康を害する可能性があります。そのため、「猫の数+1個」のトイレを用意することが推奨されています。例えば、3匹の猫を飼っている場合、4つのトイレを設置するのが理想的です。
では、なぜトイレの数を増やす必要があるのでしょうか?その理由の一つは、猫が清潔好きな動物だからです。排泄物が残ったトイレを嫌がる猫も多く、一つのトイレしかないと、他の猫が使用したトイレを避けて排泄を我慢してしまうことがあります。その結果、膀胱炎や尿路結石などの病気を引き起こすリスクが高まります。
また、猫の性格によっては、他の猫とトイレを共有することを極端に嫌がる場合があります。特に、縄張り意識の強い猫は、自分専用のトイレがないと不安を感じ、家の中で粗相をしてしまうことがあります。このような問題を防ぐためにも、十分な数のトイレを用意し、猫が安心して排泄できる環境を整えることが重要です。
トイレの設置場所についても工夫が必要です。猫は静かで落ち着ける場所を好むため、できるだけ人の動きが少ない場所に設置するのが望ましいです。また、トイレ同士を近くにまとめすぎると、猫が「トイレは1つしかない」と認識してしまう可能性があるため、複数の部屋に分けて設置するのが理想的です。
さらに、猫砂の種類にも配慮しましょう。猫によって好みが異なるため、細かい砂を好む猫もいれば、大粒の砂を好む猫もいます。多頭飼いをしている場合、猫の好みに合わせて異なる種類の猫砂を使うことで、トイレを快適に利用できるようになります。
このように、トイレの数や設置場所、猫砂の種類などを工夫することで、多頭飼いでも猫が快適に暮らせる環境を作ることができます。トイレは単なる排泄場所ではなく、猫の健康管理に直結する重要なポイントであることを理解し、適切な対応を心がけましょう。
部屋数と飼育頭数の関係とは?
猫の多頭飼いをする際、部屋数と飼育頭数の関係は非常に重要な要素です。猫は縄張りを意識する動物であり、十分なスペースが確保されていないとストレスを感じることがあります。そのため、部屋の数に応じた適正な飼育頭数を考慮することが大切です。
一般的な目安として、猫が自由に行き来できる部屋の数から1を引いた数が適正な飼育頭数とされています。例えば、3LDKの住居であれば2匹程度、4LDKであれば3匹までが理想的とされています。これは、猫がそれぞれの縄張りを持てるようにするための考え方であり、部屋が少ない環境で無理に猫を増やすと、縄張り争いやストレスが増える原因となります。
特に、多頭飼いをする場合は、猫が「隠れる場所」を確保できることが重要です。猫はストレスを感じたときに安全な場所に身を隠すことで安心します。そのため、十分な部屋数がない場合でも、キャットタワーや棚を活用して縦のスペースを作り、猫がそれぞれの居場所を持てるように工夫することが必要です。
また、部屋の広さだけでなく、トイレや食事スペースの配置も考慮しなければなりません。トイレやご飯の場所が一箇所に集中していると、猫同士の距離が近くなりすぎてストレスの原因になることがあります。そのため、複数の部屋がある場合は、それぞれの場所にトイレや食事スペースを分散させることで、猫同士がリラックスできる環境を整えることができます。
このように、部屋数と飼育頭数は密接に関係しており、猫が快適に過ごせる環境を作るためには、十分なスペースと環境整備が欠かせません。
多頭飼養届出書の義務と地域ごとのルール

猫の多頭飼いをする場合、地域によっては「多頭飼養届出書」の提出が義務付けられていることがあります。この届出制度は、猫の適正な飼育環境を維持し、多頭飼育崩壊の発生を未然に防ぐために設けられています。全国的に統一された法律ではなく、自治体ごとにルールが異なるため、飼い主は事前に自分の住んでいる地域の条例を確認することが重要です。
例えば、大阪府では2016年7月1日から、10匹以上の猫を飼育する場合に府への届出が義務付けられています。これは、猫の飼育環境が適切に管理されているかを把握し、問題が発生する前に対策を講じることを目的とした制度です。届出を怠った場合や虚偽の申告をした場合、5万円以上の過料が科せられる可能性があります。一方、東京都や兵庫県、京都府などでは、現時点では特に具体的な飼育頭数の制限や罰則が設けられていません。しかし、動物愛護法の改正に伴い、今後はより厳格なルールが導入される可能性もあります。
また、石川県では2022年4月1日から、犬や猫を合わせて6頭以上飼育する場合に「多頭飼養届出書」の提出が義務付けられました。この届出制度の目的は、近隣住民とのトラブル防止や、劣悪な飼育環境の発生を防ぐことにあります。具体的には、飼い主が適切な管理を行えているかをチェックし、必要に応じて行政が指導を行う仕組みになっています。なお、この届出制度は第一種動物取扱業者(ペットショップやブリーダーなど)や動物病院は対象外となっています。
このように、自治体ごとにルールが異なるため、多頭飼いを検討している場合は、事前に役所や保健所などの公的機関に問い合わせることが重要です。届出をしなかった場合の罰則がある地域もあり、知らずに違反してしまうとトラブルに発展する可能性があります。
また、届出を行うことで、自治体から適切な飼育アドバイスを受けられることもあります。多頭飼いは猫の福祉を守るために慎重に進めるべきものです。猫が快適に暮らせる環境を維持するためにも、ルールを確認し、適切な対応を心がけることが大切です。
参考:多頭飼育届出制度について
猫の多頭飼いと精神疾患の関連性とは?
猫の多頭飼いと精神疾患には一定の関連性があると指摘されています。これは、猫を飼うことで精神的な癒しを得る人が多い一方で、過剰に猫を増やしてしまうことで生活が破綻し、多頭飼育崩壊へとつながるケースがあるためです。特に、孤独感を抱えやすい人や、精神的に不安定な状態にある人は、猫に依存しやすく、無計画な多頭飼いに陥るリスクが高くなります。
実際、多頭飼育崩壊を起こした飼い主の特徴として、うつ病や認知症などの精神疾患を抱えていたケースが報告されています。例えば、高齢の一人暮らしの女性が「猫がかわいそうだから」「誰かが面倒を見ないといけない」との思いから次々と猫を保護し、気づけば管理が追いつかなくなった事例があります。このような状況では、猫の健康管理ができなくなり、最終的には行政が介入せざるを得なくなることもあります。
また、強い孤独感を抱えている人は、猫を家族のように感じ、より多くの猫を迎え入れたくなることがあります。特に、社会的なつながりが少ない人は、猫との生活を心の支えにする傾向があり、それ自体は問題ではありません。しかし、精神的に不安定な状態が続くと、猫を増やしすぎてしまい、適切な世話ができなくなる可能性が高まります。
一方で、猫との生活が精神的な安定に寄与するケースもあります。猫の鳴き声や毛並みを撫でることがリラックス効果をもたらし、不安を軽減することが科学的にも証明されています。特に、ストレスが多い現代社会では、猫と暮らすことで精神的な癒しを得ることができるため、猫を飼うこと自体は決して悪いことではありません。
ただし、適切な管理ができない状態で猫を増やしてしまうと、逆にストレスが増加し、精神的な負担が大きくなることもあります。例えば、経済的に厳しくなり、猫の食費や医療費の支払いが困難になると、そのこと自体が新たなストレス要因となります。また、多頭飼いでは猫同士のケンカや縄張り争いが起こりやすく、飼い主が精神的に疲れてしまうこともあります。
このような問題を防ぐためには、猫を迎える前にしっかりと計画を立て、自分の精神状態や生活環境を客観的に判断することが大切です。猫の数を適切にコントロールし、無理のない範囲で飼育することが、飼い主にとっても猫にとっても幸せな生活につながります。
また、もし多頭飼いが精神的な負担になっていると感じた場合は、動物愛護団体や行政機関に相談することも重要です。場合によっては、里親制度を活用することで、猫の生活環境を改善することができます。
猫の多頭飼いと精神疾患の関連性は、個人の生活状況や心理状態によって異なります。大切なのは、猫を迎えることで「自分も猫も幸せになれる環境を作ること」です。無計画な多頭飼いは避け、適切な飼育環境を整えることで、猫との暮らしをより良いものにしていきましょう。
総括:猫の多頭飼いは頭おかしい?後悔しないための適正な飼い方

- 猫を多頭飼いする人は愛情や孤独感が影響することが多い
- 保護活動をきっかけに無計画に猫を増やしてしまうケースがある
- 一般的に1LDKなら1~2匹、2LDKなら3~4匹が適正な目安
- 縄張り意識が強いため、スペース不足はストレスの原因になる
- トイレの数は「猫の数+1個」が理想的である
- 猫同士の相性が悪いとケンカやストレスで健康を害するリスクがある
- 無計画に増やすと多頭飼育崩壊につながりやすい
- 多頭飼育崩壊では不衛生な環境や病気の蔓延が発生しやすい
- 経済的負担が増えるため、計画的に飼育することが重要
- 一軒家でもスペースやトイレ環境を考慮しないと飼育は難しい
- 自治体によっては一定数以上の飼育に届出が必要な場合がある
- 猫との生活は精神的な癒しになるが、依存しすぎると問題が生じる
- 高齢者や精神的に不安定な人は無計画に猫を増やしやすい傾向がある
- 猫を迎える前に自分の生活環境や管理能力を冷静に判断することが必要
- 適切な頭数と環境を整えることで、多頭飼いを成功させることができる